
素人テナーが選ぶ、イタリア歌曲集ベスト10。
今回は、7位にランクインした、Danza, fanciulla gentile(踊れ、優しい娘よ)。
作者は、フランチェスコ・ドゥランテ(Francesco Durante)。
バロック後期に活躍した、シチリア生まれの音楽家。
この曲の何が良いかといって、激しく上下するアップテンポの旋律に、知らず知らず、身も心も飲み込まれそうになる。
前奏からスゴイ。
ダダダダダッダッダッダ~ン♪
これは、本当にバロック時代の音楽なのだろうか、と思ってしまう。
どちらかと言えば、静かで内向的な曲想の多いイタリア古典歌曲において、群を抜いて圧倒的な存在だ。

この曲のことも、また、他のほとんどのイタリア古典歌曲と同様に、レッスンまで全く知らなった。
そして、はじめての時から好きでたまらなくなった。
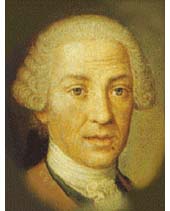
日本では、元禄文化が花開いて、赤穂浪士が討ち入りをしたころ。
1684年、シチリア王国に生まれ、1755年にナポリて没している。
幼いときにナポリに移り、イエスキリスト貧民音楽学校に入学した。
この学校は、後にナポリ音楽院として統合され、ドニゼッティやトスティ等を輩出している。
その後、彼は、アレッサンドロ・スカラッティ等に師事。
この、アレッサンドロ・スカラッティは、生涯に59もの正統派オペラ(オペラ・セリア)を作曲したイタリアンバロック中期の巨匠。

なにしろ、この当時のナポリは、パリ、ロンドンに次ぐ、ヨーロッパ第三位の大都市。
それ以上に、「世界の音楽の首都」とも評されるほど、音楽が盛んな土地柄だった。
18世紀当初には、特にオペラが隆盛して、劇場が相次いで建設されていた。
音楽事情に疎い、普通の日本人の感覚からすると、「なんでナポリ?」、と思う。
だけど、スペイン継承戦争のゴタゴタを経て、ハプスブルクの支配に代わった以降も、
ナポリは、音楽院が輩出する多才な若者たちの活躍により、世界の音楽の中心地として発展していた。

ドゥランテは、スカラッティが立ちあげた、〈ナポリ楽派〉を受け継いで活躍するのだけど、
作品はもっぱらミサやレクイエムなどの宗教曲が中心だった。
では、歌曲、Danza, fanciulla gentileは、どのような経緯で誕生したのだろうか。
この歌は、オペラアリアではなく、作詞者不明のアリエッタとある。
アリエッタの定義は、規模の小さなアリア(=独唱曲)。
ということで、この説明をそのまま解釈すると、「詠み人知らず小曲」 となる。
訳詞の、字面からの印象になるけど、気の利いた比喩や表現の深みを、あまり感じない。
オペラアリアのように、〈避けられない宿命〉のような壮大なテーマというよりは、
似たようなものが他にもありそうな、庶民的な感じ。

Danza fanciulla gentile,
al mio cantare.
Gira,vola,leggera,sottire,
vola al suono dell’onde del mare
senti il vavo rumore
dell’aura scherzoza.
che con languido suon parla al core
e che invitaba a danzar senzapoza.
踊れ、優しい娘よ、
私の歌に合わせて。
回れ、飛べ、軽やかに、しなやかに、
飛べ、海の波の音にあわせて。
悩ましい響きで心に語りかけ
休むことのない踊りに誘う戯れ心のそよ風の
美しい音を聞け。

残念なことに、オペラの場合と異なり、この歌の出自については、あまり多くの情報を得ることができなかった。
そんな中、南アフリカのピアニスト、アルバート・コンブリンク氏(Albert Combrink)が面白いブログを書いているのを発見する。
曰く、もともとこの曲は、ドゥランテが学生用に作った教材のようなもので、
歌詞がついていなかったと考えられるのだそうだ。
それが、現在のような歌詞つきで世の中に知られるようになったのは、
19世紀に発行された〈Aria Antiche〉という歌集において。
その中には、ドゥランテ作とされるものが2曲納められているのだけれど、
どちらもドゥランテ自身が編纂した作品集には入っていない。
これらのことから、もとは本人が作品とは思っていない、たとえば学生用の練習曲のような存在であり、
それらに、19世紀の歌集作成時に、編集者により歌詞がつけられたのではないか。

速度や強弱表記についても、バロックのころにはないものが使われているので、
メロディー以外は、19世紀の人が、100年前の音楽を想像して作ったものと考えられている。
と、いうことで、仮にこの説明が正しいとすれば、コンコーネのどれかに歌詞をつけて歌っているようなものかなぁ。
歌詞が、ありきたりな印象であることも、
曲想が、どこかバロック離れしていると感じたのも、
恐らく19世紀にリメイクされたときのアレンジの結果なのだろう。
だからといって、この曲の価値を貶めることにはならないと思う。
原曲の素晴らしさを後世の人々が引き出し、歌い繋いできた賜物なのだから。
歌い手にとって、歌心をそそられるような上行下音階だったり、心地よいリズムの伴奏だったりするのは、
原作者とリメイク者の双方が存在したからだし、どちらか一方が欠けても達成できなかった結果なのだと思う。

では、現在の演奏はどうなのか。
女声・男声を含めて、多くがあるのだけど、ピアノ伴奏で、畳み込む様な感じのものが多い。
こういうのが、現在のこの曲に定着した、演奏のイメージなのだろう。

ピアノ版の中では、やはり、パバロッティの演奏が好きだ。
レガートとマルカートの歌い分けといい、後半のドラマチックな盛り上げ方といい、『さすが』の一言。
オーケストラ版としては、カレーラスやホロストフスキーの演奏がある。
うち、ホロストフスキーのほうは、〈Aria Antiche〉全曲をカバーしていているアルバムからのもの。
チェンバロと他の楽器とのアンサンブルに、ホロストフスキーの控え目な歌い方が、バロックらしさを彷彿させている。
また、ドゥランテの作として、〈Aria Antiche〉に編入されている、もう一曲のほう。
"Virgin Tutto amor" (愛に満ちた処女よ)。
こちらについては、カウンターテナーのクリステアーン・フーゲの演奏が美しい。
前述のコンブリンク氏によれば、カストラートの演奏に近いものを感じるのだそうだ。
パイプオルガンの調べに乗って、透明な歌声が天空に響いているようだ。
ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派と進むにつれて、キリスト教の束縛から、音楽は解放されてゆく。
より自由に、より奔放に。
"Danza, fanciulla gentile”の存在が、見事にその過程を示していると思う。
ほんの小さな歌曲ではあるけれど、バロックと、その後の音楽との融合を示しつつ、
300年後の現在まで、歌い手の心をつかんで離さない。
そこには、作者ドゥランテが、伝統を受け継ぎ、真剣に曲想を探求して、
教育を通じて後世に伝えようとした、
音楽への強い思いがあったからなのだろう。

コメントをお書きください